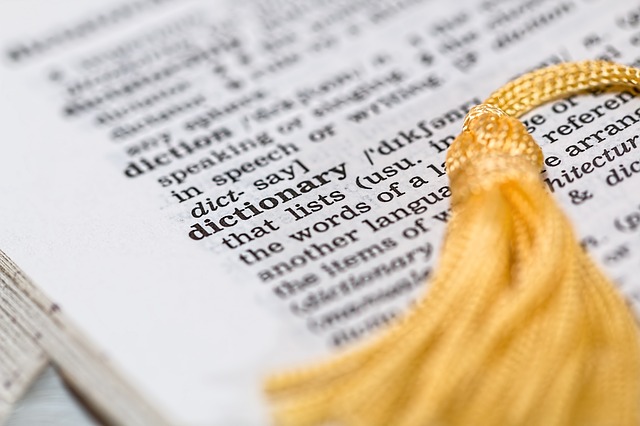Ryet
2018-08-18T13:08:00+09:00
【用語辞典】資格に関する用語の解説
2018-08-18T04:08:42Z
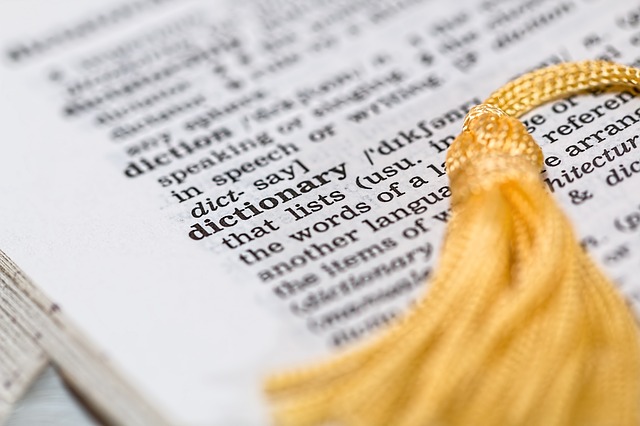
資格を知るにあたって専門用語に近いものも多く存在しますので簡単にまとめてみました。
資格の種類
資格は「国家資格」「公的資格」「民間資格」「国際資格」の4つにわけられます。さらに国家資格は業務独占資格・必置資格・名称独占資格の3種類にわけられます。
国家資格とは
法律に基づいて国または国から委託を受けた機関が実施する資格になります。
例えば国家資格である「医師免許」であれば医師法にこう記されています。
第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
国家資格は大きくわけると業務独占資格・必置資格・名称独占資格の3種類にわけられます。
業務独占資格とは
ある業務に対してその資格を持っていないと業務自体を行うことができないと法律で定められている資格になり、国家資格の中で最も強い資格になります。
例えば建物の設計は建築士の業務独占、薬の調剤業務は薬剤師の業務独占、税務申告と税に関する相談業務は税理士の業務独占です。
中には力の弱い業務独占資格もありますが基本的には資格としての力が最も強く、独立も可能になる資格も多いです。
手に職をつけたい方におすすめ!業務独占資格ランキング
業務独占資格は「資格がなくては行えない業務」に必要なものなので数ある資格の中でも強力!手に職をつけたい方にぜひおすすめしたいです
必置資格とは
ある事業を行うには必ず〇〇人以上の有資格者を設置しなければならないと法律で定められているタイプの資格です。
有名どころでは宅地建物取引士。不動産営業所には宅地建物取引士を5人に1人の割合で設置しなければならないと宅建業法で定められており、人数を満たしていなければ営業できません。
他にも一定以上の危険物を取扱う施設には危険物取扱者を配置しなければなりませんし、マンション管理会社の事務所には管理業務主任者を配置しなければなりませんし、旅行業務を行う営業所には旅行業務取扱管理者を設置しなければなりません。
業務独占資格ほど力が強いわけではありませんが必置義務があるために就職や転職に強くなる傾向がある資格です。
必置義務がある就職や転職に強い人気資格ランキング!
法律で有資格者を設置しなければならないと義務付けられている必置資格をまとめてみました。就職に強いものから専門性の強いものまで!
名称独占資格とは
業務独占や必置義務などはありませんが有資格者以外はその資格の呼称を名乗ってはいけないと法律で定められている資格です。
厳密には業務独占資格のほとんど名称独占でもあり、例えば看護師は業務独占資格ですが看護師と言う名称は名称独占になっています。
ですが一般的に名称独占資格と言うと業務独占も必置義務もない国家資格のことを指します。
有名どころの名称独占資格を例を挙げると中小企業診断士、情報処理技術者試験、技術士、介護福祉士、管理栄養士などがそれにあたります。
資格としての力は最も弱く、正直露骨に天下り臭が漂う資格もあったりするのですが、中には非常に評価の高い資格もあったり、ほとんど業務独占・必置資格のような性質を持つ名称独占資格もあります。
公的資格とは
国家資格ではないが公的な性格を持った民間団体や財団法人等が主催している資格のことを言います。
商工会議所法により商工会議所主催の検定試験は公的資格となっているので日商簿記や販売士検定、福祉住環境コーディネーターは公的資格になります。
都道府県が主体となって実施する資格も公的資格になり、よく国家資格と間違われることで有名な介護支援専門員(ケアマネージャー)は公的資格になります。都道府県が主体となって試験を実施しているため国家資格ではありません。
また公的資格との差が少しあいまいなところがある登録販売者ですが当ブログでは国家資格として扱っています。
登録販売者も都道府県が主体となって試験を実施しているのですが、国が定める法に基づいて特定業務が認められているため一般的には国家資格と区分されます。
民間資格とは
民間団体が実施している資格です。
医療事務管理士やインテリアコーディネーターのように特に就職に強くなるわけでもない民間資格も多いです。
しかしTOEICのようにものすごく有名でスコアによっては就職にも大きく影響するものや、臨床心理士のように非常に専門性の高い民間資格も存在します。
国際資格とは
日本の資格の多くは日本でしか通用しない資格ですが、海外でも通用する資格を国際資格と呼ぶことがあり、当ブログではそう言った資格を国際資格と明記しています。
ワードやエクセルが使えることを証明するMOSや、世界標準のプロジェクトマネージメントのノウハウPMBOKを理解していることを証明するPMPなどがそれにあたります。
資格関連用語
当ブログで比較的頻繁に出てくる用語をまとめます。
か行
高度専門士とは
日本では4年制の専門学校(専修学校専門課程)のうち一定の要件を満たしているものが卒業生に授与する称号のことを指します。
高度専門士は大学卒業者と同等以上の学力があると判断されるため大学院の入学資格が与えられます。
さ行
士業とは
「士」のつく国家資格の職業のことを言います。
中でも戸籍や住民票の請求権が認められている8つの資格は8士業と呼ばれることもあります。
8士業は弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士の8つになります。
職業訓練施設とは
職業能力開発、技能講習など職業訓練を行う施設のこと。
職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校などが職業訓練施設にあたります。
専修学校とは
一定の基準を満たしているいて都道府県知事の認可を受けている学校のことで、専修学校の一種が私たちのよく知る専門学校のことになります。
専修学校には専門課程・高等課程・一般課程の3種類があり、専修学校専門課程だけが学校教育法で専門学校の名称を用いることが許可されているため、学校名に専門学校と入っていれば専修学校専門課程のことを指すことがわかります。
大学教育よりも実践的な教育を行い、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする学校です。
専門士とは
日本では2~3年制の専門学校(専修学校専門課程)のうち一定の要件を満たしているものが卒業生に授与する称号のことを指します。
専門士は短大卒業者と同等以上の学力があると判断されるため大学への編入の資格が与えられます。
た行
ダブルライセンスとは
2つ以上の資格を持っていることを意味します。組み合わせによっては少々弱い資格でもものすごく強いものに化けることもあります。
個人資産運用のプロフェッショナルであるFP(ファイナンシャルプランナー)と確定拠出年金のプロであるDCプランナーは非常に相性がいいです。
他にも経営コンサルタントの資格である中小企業診断士は、税に関する相談に乗れる税理士、就業規則を請け負ったり助成金コンサルタントができる社会保険労務士、飲食業や建設業など起業する際に許認可手続が必要な際に代行できる行政書士などと相性がよくなります。
またエネルギー管理士は場合によっては研修+実務経験だけで取得することもできる資格で単体では弱いですが、電気主任技術者と建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)と組み合わせることでビルメン業界ではエリート級となり非常に有利になります。
ま行
免状の交付とは
免状とは免許の証として交付される証明書のことを指し、交付とは引き渡すことを意味します。
例えば電気主任技術者は「電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければならない」と定められている必置資格ですが、電気主任技術者試験に合格しただけでは免状の交付を受ける資格を得ただけであり、免状の交付を受けてはじめて必置資格としての価値が出ます。
ら行
リスクヘッジとしての資格
リスクヘッジとは金融用語・ビジネス用語として「危険を回避する」と言う意味で使用されています。
riskは危険・恐れ、hedgeは投資などにおいて回避すると言う意味があります。
リスクヘッジとしての資格は、倒産することになったり職がなくなったとしても不況にも強い資格を持っていることでいざと言うときに役立つかもしれない資格と言う意味で使われています。
リスクヘッジとしての資格の例として、どんな企業でも従業員が50人以上いれば必ず設置しなければならない必置資格である衛生管理者があげられます。