
食品衛生管理者とは、食肉製品や乳製品などを製造・加工する施設の営業所ごとに設置しなければならないと定められている必置資格である国家資格になります。
無関係の業種からはたびたび食品衛生責任者と誤解されがちな資格ですがまったく違います。
この記事では食品衛生管理者に関する情報や取得方法、そして食品衛生責任者との違いなどを詳しく解説していきます。
食品衛生管理者の特徴
食品衛生法で定められた必置資格になります。
食品衛生管理者の仕事内容

全粉乳、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング、規格が定められた添加物を製造する業種では、食品衛生管理者を設置しなければならないと食品衛生法で定められています。
食品衛生法 第四十八条
乳製品、第十条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
食品衛生管理者は設置された施設において製造・加工段階での衛生管理を行うことが仕事になります。
あくまで特定の業種のみで必要となる資格ですので、就職にとても強いと言う資格ではありません。ですがその特定の業種においては若干有利になる可能性もあります。
食品衛生責任者との違いは?

食品衛生管理者(かんりしゃ)はあくまで特定の業種で必要になる資格ですので、比較的有名な食品衛生責任者(せきにんしゃ)と一緒にされがちですが実は全く別の資格です。
食品衛生管理者はさきほども紹介したように食肉製品や乳製品、食用油脂などを製造・加工する施設において設置しなければならない必置義務のある国家資格です。
食品衛生責任者は飲食店や食品製造施設などにおいて設置しなければならない公的資格になります。
食品衛生責任者は主に飲食店開業時などに意識しなければならない資格ですので比較的有名ですが、食品衛生管理者はかなり限られた業種において必要な資格なのでごちゃごちゃにされがちですが別の資格になります。
食品衛生責任者についての詳しい情報は以下の記事にまとめていますのでよろしければどうぞ!
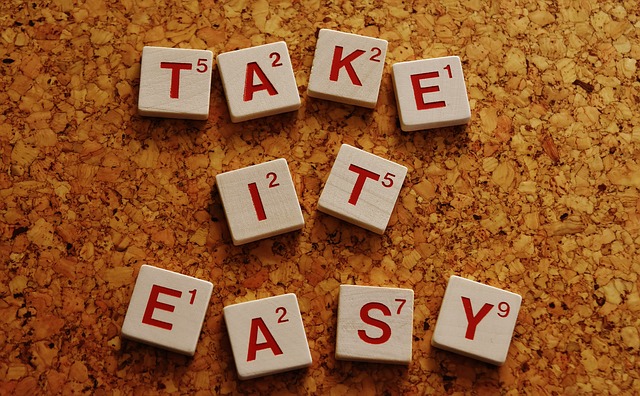
食品衛生責任者は飲食店開業時に必要!講習だけで取れますよ
食品衛生責任者は1日だけの講習で取得できる資格で飲食店や特定の食品製造業にて衛生上の危害防止のため必ず有資格者が必要になります。













